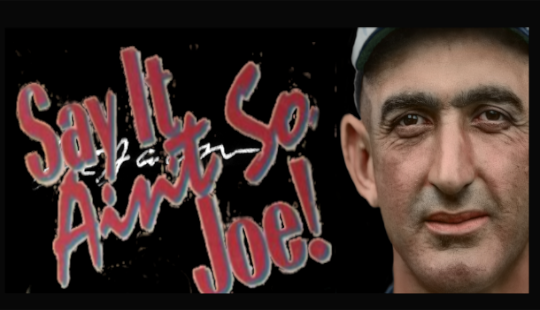Negative legend
Field of Dreams、はだしのジョー(2)!
ジョーは皮肉にも3年ごとに、新しいチームに加わり、記録的な好成績をあげるも、翌年になるといなくなるという繰り返しで、今回で3度目だった。
そのクリーブランドは、大リーグとしては数奇な運命をたどってきた。ナショナルズを名乗っていた時代、鉄道王と知られたロビンソン兄弟が金銭がらみで買い取った。が、かれらの目に余る守銭奴ぶり、いくつものさもしい行為がファンとの確執を深め、全米に面白おかしく報道され、ついにはチームを崩壊させるにいたった。そして、一度はなくなったチームを、1901年、ブルースというチーム名でアメリカン・リーグ創設時に復活した。
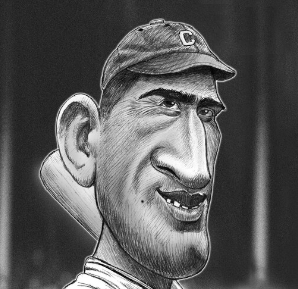
そんな翌年、三冠王をとったばかりのナポレオン・ラジョイこと、ラリー・ラジョイがアスレチックスから加入した。偉大な大リーガーでもあったかれは、フィラデルフィア・フィリーズ出身だったが、同市のアスレチックスに移籍。これに異を唱えた球団は提訴して、ラジョイはフィラデルフィアではプレーできなくなり、スパイダースと名乗っていたクリーブランドに移籍した。そして、チーム名そのものも一般公募でナップスと変えてしまっていた。
後半戦20試合に出場して、ジョーは打率379、うち8本がホームランという好記録を残したものの、そんな時に、
「今日のように大きくなった大リーグでは、読み書きが出来ない男が成功するはずがない」
と、当時の有能な記者であったヒュー・フラートンがいってのけたのだ。それはまさしく、ジョーの転落を予言したかのような言葉だった。それはまた、かれは前述したかの悲痛な叫び声をあげさせた少年を新聞記事で描写した張本人でもあった。
だが、1911年、いつのまにかジョーはくつろいだ気分になっていて、あのサウスカロナイナなまりのゆっくりとした口調で、一部のチーム・メイトとも会話をはじめ、冗談をもいい合うようになっていた。が、大半のナップスの選手たちからは、
「裸足のいなかモン」
と、カゲ口をたたかれていた。が、ジョーの活躍はシーズン当初から、すさまじかった。37試合連続ヒット、12試合で26本のヒットを放つなど大活躍だ。
あらゆるベンチ・ジョッカーたちがヤジを飛ばすも、ジョーはめげなかった。不要な力をいれずに、ブラック・ベッティをいつもと同じやり方で握り、右手の小指はバットの一番下の握りにかけていた。
なんの小細工もせず、ただきた球を鋭く振りぬき、ライナー性の打球を飛ばす。それが、ジョーのバッティング・スタイルだった。タイ・カップなどのように、バットに握り方をその場で変えることもなかった。
ただ、かのウォルター・ジョンソンにだけには、バットを一握り残して狙いすまし、アテにいったものだ。そのかいあって、通算打率は5割と高い。
「何一つ弱点はないんだ。ジョーに試合をかきまわされずにすんだ日は、それだけでうれしかった」
と、ジョンソンは語ったものだ。
ジョーの打球はライン・ドライブで低く飛ぶので、内野手のグラブが吹っ飛び、その打球の勢いで内野手がたたきつけられても、それでもエラーになってしまう。
あの名外野手トリス・スピーカー(レッドソックス)でさえ、打球が音を立ててまっしぐらに飛んできて、グラブを構えたがすでに遅く、首を直撃して、ランニング・ホームランを許したこともあった。そんな打球であったからこそ、外野フェンスを直撃しても、勢いが良すぎて内野の近くまで大きくバウンドして戻ってきて、たんなる単打にとどまることも多かった。
その年、22歳になったジョーの初のフル出場ともなった。408の打率。233本のヒット数はイチローがその記録を抜くまで、新人の最高記録だった。が、おしくも首位打者のタイトルは、カップに奪われた。
カップの自伝によると、そのときのおもしろいハナシが伝わっている。同じ南部出身ということもあって、
「タイ兄貴、調子はどう? うまくいってるかい? 」
と、いつものようにジョーが話しかけてきたが、その日に限って、カップは冷淡な表情をくずさず、ジョーを見つめていただけ。すると、ジョーのなごやかな笑みも消えて、
「なあ、タイ。いったいどうしたんだい? 」
とたずねるも、カップは何もいわず、素通りしてしまった。ジョーは気になって、追いすがってもう一度訊ねようとすると、
「オレの側に近づくな」
と、カップはどなった。ジョーはひどく傷つき、バッティングの調子さえ狂ってしまった。と、まあ、こんなぐあいでカップは悪知恵を働かせ、ジョーを追いやったと書いている。
そのジョー自身はというと、
「カップは、初めからボクをリードしていた。ヒットの数だって、カップのほうが多かった」
と、その当時を回想したものだ。続く1912年、13年と最多安打を記録。ジョーはまさに、過去のいかなる打者よりもぬきんでた才能を発揮しはじめたのだ。
さてと、選手の縁起かつぎにはいろんなものがあるが、ジョーのそれは、ヘア・ピン集めだ。打てなくなると、その集めたヘア・ピンをばらまき、またひとつひとつ集めるってわけだ。
審判に対するクレームも少なかった、というか、一度もなかった。ジョーの一番厳しい抗議は、首をかしげることだったのだ。そんなジョーだったからこそ、ファンはジョーを愛した。それは、ジョーと対戦した選手たちもそうだった。
デトロイトのキャッチャーは、ジョーにヒットを打たさないために全力をつくしたが、その日もカンペキなヒットを2本打たれ、その第3打席目、
「このシーズン、どんな球を投げても打たれてしまった。今度はどんな球をご希望かね」
と、ジョーに訊ねた。すると、
「外角高目がいいね」
とこたえると、ホントにその球がきた。ジョーはレフト前にはじきかえした。また、アスレチックスの頭脳派であり、最強の投手であるチーフ・ベンダーはいみじくも、
「ジョーには何を投げてもムダだと結論がでているよ」
と語ったものだ。
その一方で、カティもまた、球団のマスコット的存在だったようだ。輝く微笑み、淡いブルーの瞳、小奇麗なまでの服装。ジョーの妻・カティはほかの選手の妻たちを圧倒していた。
その彼女は、バックネット裏のお気に入りの一番うしろの席で観戦し、ジョーがヒットを打つと声援をおくり、倒れるとタメ息をついた。ジョーは、
「1マイルもボールを飛ばさない限り、カティはヒットとして認めてくれない」
と、よくこぼしたものだ。しかし、それも7回のウラまでだった。試合に何が起ころうとも、7回が終わるとさっさと帰ってしまうのだ。
「うちに帰って夕食をつくらなければならないから。家で食べるほうが、ジョーの健康にはいいのだ」
ということである。
参考文献:『折れた黒バット』(ドナルド・グロップマン著 小中陽太郎訳 ベースボール・マガジン社刊)